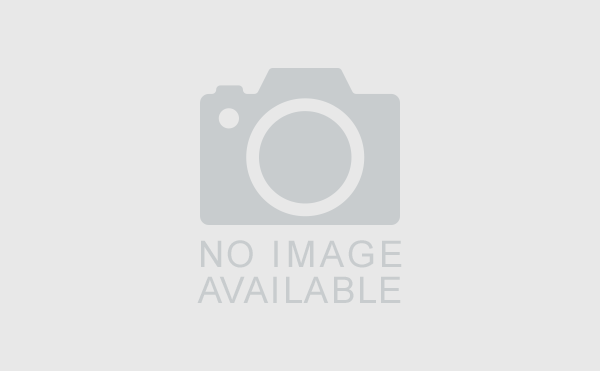第1回ビジコン-八木尚美

八木尚美
障害者家族専門ビジネスコミュニティ
《 事業概要 》
障害者家族専門の起業家のコミュニティを提供する
ケアする人それぞれに様々なケア体験があり、持っている資格や知識がある。その経験を活かして福祉事業所の立ち上げ、ケアに関わる事業で起業する方たちが一人で悩まずコミュニティで相互支援する事で成功していく。また、その人たちの事業が地域で連携を行い、介護者の社会的自立を目指すのと人材育成も目指す
ケアに関わる人が孤立しない環境をつくる 自分の想いを志事にし、社会起業家になる
会員費・コンサル料・
《 経歴・想い 》
私は進行性の難病があり、身体障害を持つ弟を支える現役ケアラーです。
16歳から22歳までの間、高校生の頃から母の介護をしていました。
私のように障害のあるきょうだいがいる人たちは、障害者の介護に必死で自分の人生に我慢している、楽しそうにしていない姿をみて、何とかしなくては、自分も期待に応えなきゃとなって自分のやりたいことを後回しにし、ケア要員として期待されていることに対して自分の存在意義に何だろうと悩んでいます
母の晩年、私にだけ「死にたい」と繰り返し訴えていました。「こんな風に生きたくない」という心の叫びを20代の私は理解せず、自分がいるのになぜと自分を責めてしまった後悔があります。
また、亡くなる直前までもがいて死ぬことに何もできないもどかしさがあり、ずっとどうすればよかったのかと悩みを抱えました。だからこそ、後悔なく生きるにはの問いがずっとありました
そんな中22歳の時に母が亡くなった数日後、私は突然体が動かなくなり、「このまま私の人生が終わるかもしれない」と強く感じました。そこから、「やりたいことをやってみよう」と決意し、以前から興味があった学校図書館司書の道へ進みました。
図書館では、子どもたちが本に親しみ、時に心の居場所となる環境の中で充実した日々を過ごしていました。しかし、障害を持つ(きょうだい)や、今でいうヤングケアラーの子どもたちと接する中で、彼らがケアがにちじょうにあること、そして彼らの親が誰にも頼らず家族だけで抱え込み、苦しんでいる姿を目の当たりにしました。
「私の子どもの頃の30年前と同じ課題が、今もなお解決されずに残っているのか」
この現実に衝撃を受け、負のバトンを手渡していいのかと悩んでいた時、キャリアコンサルタントという国家資格を取得することで、キャリアや人生の支援ができると知り、資格を取得しました。
さらに、きょうだい支援を行う団体や支援者と出会う中で、自分自身が「ヤングケアラー」だったことを初めて自覚しました。まだまだ社会では「家族でケアを頑張るべき」という価値観が根強く、
ケアに疲弊する大人を見て、子どもたちは我慢してしまいます。そして、その我慢が積み重なり、子どもの頃から「どうせ無理だ」と夢を諦めることに繋がってしまうのです。
この出来事からケアがあっても「自己実現ができる社会をつくりたい」この想いから起業を決意しました。
ケアは100人いれば100通りのケアがあります。メディアに登場するようなキレイごとや感動的に毎日を過ごせるわけではありません。
障害者福祉の現場や起業家の仲間と出会う中で、「障害者の家族で起業している人たちがそれぞれのケアの経験を持ちより連携すれば、社会を大きく動かせるのではないか」と考えるようになりました。
さらに「親亡きあと問題」も、家族だけで抱え込む必要はないのではないかと感じています。
障害者の子どもが成長するということは、親も年齢を重ねていくこと。
そして、親亡きあとは親もきょうだいも障害者が「どう生きていけばいいのか」と思い悩みさまざまな福祉や行政の手続きをしても万全ではありません、時には親は「障害のある子どもが亡くなった後に自分も死にたい」と思ってしまうほど、未来に対する不安が深刻です。 きょうだいも自分の人生があり、就職、結婚、海外へ行くなどの時に自分の意思を曲げて行動することもあり、後悔をしているきょうだいたち老います。この問題を解決するためには、家族が孤立せず、仲間と連携できる社会づくりが不可欠です。
さらに、「18歳の壁」という問題もあります。特に重度心身障害者の場合、支援学校卒業後の受け入れ先が極端に少なく、結局「自宅で過ごす」しか選択肢がない家庭も多いのが現状です。加えて、地方による福祉制度や事業所の格差も大きく、支援を受けられる環境が均等ではありません。
そのため、保護者が自ら事業所を立ち上げるケースもありますが、起業のノウハウがないため継続が難しく、また同じ境遇の仲間も少ないのが現実です。
次に、障害のある子どもを育てる家庭では、治療や放課後等デイサービスの送迎問題が常につきまといます。
加えて、支援学校卒業後に通う福祉事業所も、開始時間が9~10時、終了時間が15~16時と短いため、フルタイム勤務が難しくなり、短時間勤務や退職を余儀なくされるケースも少なくありません。
介護と仕事の両立問題が発生するのです。介護は終わりがありません。
「働きたいのに働けない」そんな状況の中で、「自宅でできる起業」を目指す人も増えていますが、集客などの課題に直面し、思うように事業を継続できないことが多いのです。
私自身、起業家コミュニティに所属し、仲間と共に切磋琢磨しながら「自分の幸せ」と「相手の幸せ」を目指して活動することで、一人ではなく、支え合いながら事業を発展させることができると実感しました。
だからこそ、障害者家族専門のコミュニティを作り、互いに支援しながら事業を展開できる場を作りたいと思っています。
このコミュニティがあれば、 障害者の家族が連携し、情報やノウハウを共有できる 、 一人で抱え込まずに、仲間とともに事業を継続できる 「親亡きあと」の不安を軽減し、安心して未来を考えられる社会がつくれる 私はこの想いを胸に、「誰もが自己実現できる社会」を目指して、共に支え合える場を築いていきます。