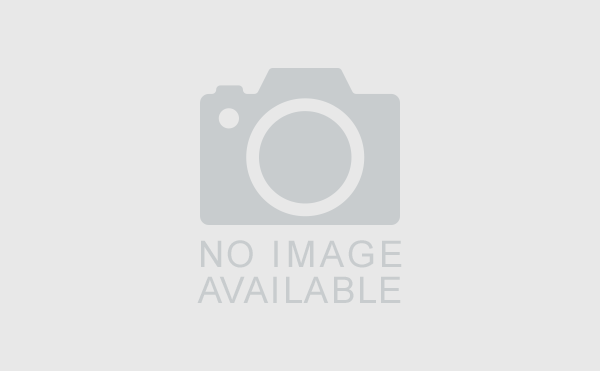第1回ビジコン-にゃにーosaka

にゃにーosaka
就労支援施設B型×保護猫シェルターにゃにーず事務所
《 事業概要 》
一般雇用が難しいが社会で自分らしく生きたいと願う障がい者の雇用や居場所を創出する。障害者による保護猫シェルターカフェの営業。地域とのかかわりで障害者は社会に生きる一員であると感じることができ、猫には新しい家族との出会いの場ができ殺処分ゼロに近づける。カフェに来るお客様の利用料が障害者の雇用と猫の暮らしを支えます。
《 経歴・想い 》
日本の障がい者人口をご存じですか?身体・精神・知的障がい者の在宅、施設入所を含めて推計1164万人、日本の人口の9.3%にあたります。では、現在日本で行われている犬猫の殺処分数はご存じですか?約1万2000頭が税金を使われて殺処分が行われています。障がい者・犬猫どちらも生きることに支援を必要とする存在ですが、支援を受ける側の存在でしかないのでしょうか。私は互いに支援しあえる存在ではないかと考えていました。
私は15年前に大好きな猫を家族に迎え、猫好き仲間とつながっていくうちに日本の犬猫の置かれている現状を知りました。様々な理由で飼えなくなった、不適切な飼育で異常に増えてしまった等、人間が起因となり劣悪な環境で生き、命を全うできない動物たちが数多く存在しています。生まれてきたのに生きることを許されず、人間の手によって無駄に殺されているのです。いったい人間に何の権利があるというのか。行政が発表している殺処分数の減少の裏には、このような状況を少しでも改善したいと保護活動をする人たちが身銭を切って自分の時間を使い、医療処置を施し、預かりをしながら里親を探しているという現状があります。それでもなくならない不幸な命。人間の在り方がとても自分勝手に思えて、現在は仲間と保護に関する啓蒙活動を行っています。
また、私は保育士として保育園や学童、のちに障がい児童のための療育施設である放課後デイサービスで多くの子どもたちに接してきました。デイサービスに通う児童の保護者と面談をすると聞こえてくる悩みは「この子には将来居場所があるのだろうか。社会で生きていけるだろうか。自分たちが死んだ後に残されたこの子はどうなるのだろう?」という不安と悩みでした。児童の保護者の話を聞いているうちに保護猫シェルターが障がいのある人たちの居場所にならないだろうか?猫も障がい者も人の支援を必要とする存在ではあるが、彼らが相互に支援しあってもよいのでは?保護猫シェルターが障がい者就労支援施設B型になったらどちらにも居場所ができるのでは?そんな想いから取り組みの第一歩として一軒家を借りて個人で保護猫シェルターを始めました。しかしながらすべてを自分で賄うシェルターだったので現在は1000万円の自己資金を失いました。でもこういった自己犠牲によりつぶれていくボランティアはたくさんいます。これも一つの社会課題だと思っています。
自己犠牲によるボランティア活動を終わらせたい。行政を巻き込んでいくことで保護猫活動への取り組みやすさ、保護活動家たちの育成や仕組みつくり、保護活動をする人たちの横のつながり、行政との協働の取り組みから法改正などに取り組んでいきます。また、就労支援施設の利用者の定着がなされない事も福祉事業に終える課題となっています。理由の一つとして職員の質の低下があげられています。研修制度を充実させて障碍者の特性の理解や関わりの工夫を自らが行えるように職員の育成にも力を入れていきます。
現在、私のシェルターでは47匹の猫が暮らしています。猫のお世話には愛情と手間が必要ですが、これが障害のある方たちの仕事になりうると考えています。就労支援施設A型での就労は難しいが、B型の施設では能力を持て余す方々の雇用を生み出すことで障害のある方々の選択肢が広がるし、人とかかわることの難しい、物事を進めるのに時間を必要とする、動物が好き、そんな人たちが自らの個性を発揮しながら社会参画をはかれたら、そんな場所がある地域は人にも猫にもとても暮らしやすく生きやすいのではないのでしょうか。生きること、暮らすこと、自分らしくあることを表現していってほしいと思います。
どんな命もその命らしく生きることのできる社会でありますように